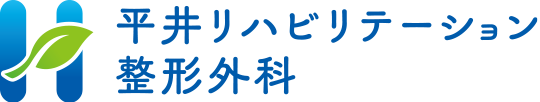自律神経について ~その1~
2025年5月12日
朝晩の寒暖差が大きくなったり、環境の変化で体調を崩したりしていないでしょうか?
この時期の不調は自律神経が乱れていることが関係しているかもしれません。
自分の自律神経がどういう状態なのか、整えて体調を改善するためにはどうしたらいいのかを2回に分けて解説していきたいと思います。 今回の内容は自分の自律神経をチェックする方法についてです。
理学療法士の片岡が解説していきます。

まず自律神経とはなんなのでしょうか。
自律神経は、交感神経と副交感神経の2つの他にも内臓求心性繊維と呼ばれる神経があります。今回は内臓求心性繊維については割愛しますが、この名前からも内臓との関係が深いことがうかがい知れます。自律神経は脳もしくは脊髄から出て、血管など全身の内臓につながっています。
そして自律神経の役割は体内環境の維持、つまりホメオスタシスにあります。ある一定の範囲に血圧や体温など生命維持に必要な体内環境を維持することをホメオスタシスといいます。
では自律神経の不調はどのような症状を引き起こすのでしょうか?
自分の自律神経がどのような状態なのかを推測するのに良い分類があります。
今回はアメリカの自律神経専門医であるDavid Goldsteinが提唱する分類方法を紹介します。彼によると自律神経症状のタイプは大まかに4つに分類されます。
- 交感神経の過活動
症状:血圧が高め、頻脈、汗が多い、高血糖、震え、鳥肌、唾液がねばつくなど - 交感神経の低活動
症状:めまい、ふらつき、食後にクラクラする、汗が少ない、疲労感、低血糖など - 副交感神経の過活動
症状:唾液が多い、徐脈、吐き気、下痢、胃酸過多、涙が多い、トイレが頻回など - 副交感神経の低活動
症状:ドライマウス、便秘、ドライアイ、頻脈、排尿がスムーズにできないなど
以上の4つのタイプにすべての症状が分類できるわけではないですが、特徴を理解するには良い分類方法です。
あなたは4つのタイプのどれに当てはまりそうでしょうか?複数のタイプに当てはまるような方も居たかもしれません。
次回のブログでは自律神経機能を改善するための方法について解説していきます。